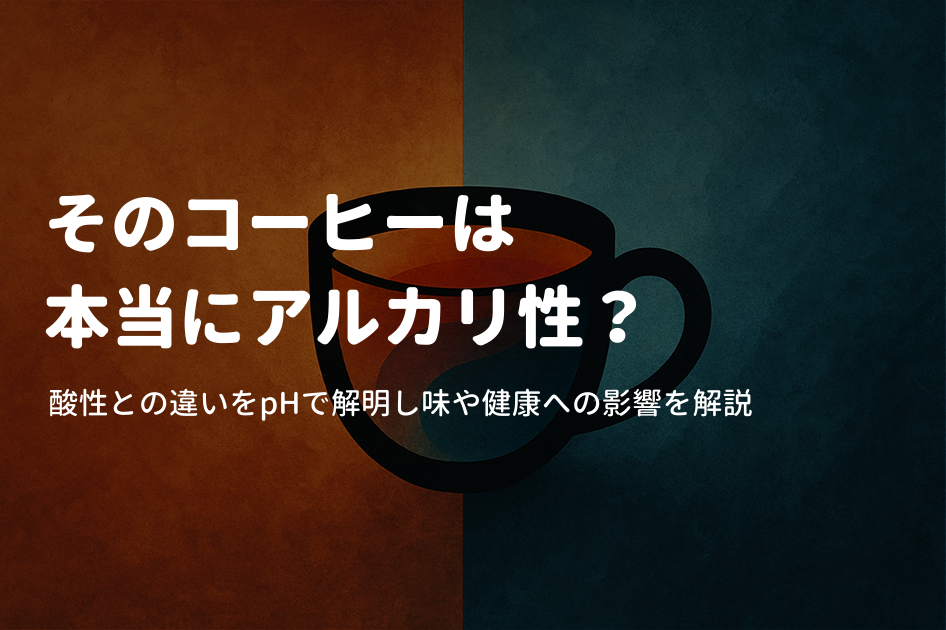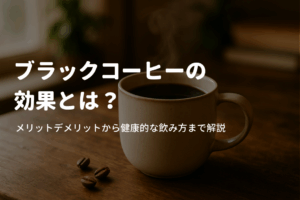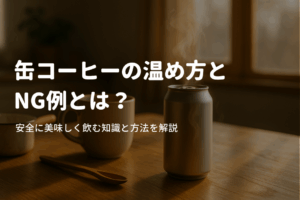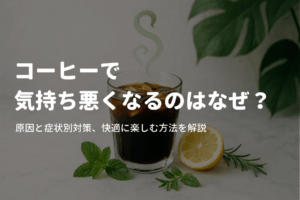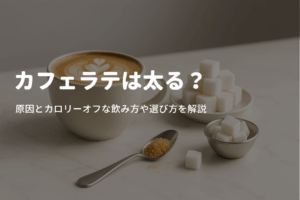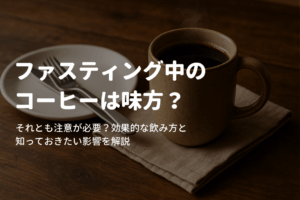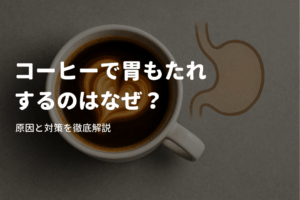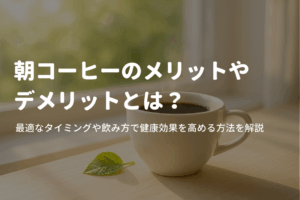「コーヒーは酸性?それともアルカリ性?」この疑問、コーヒー好きなら一度は考えたことがあるかもしれませんね。
実はこの答え、一言では言えないんです。コーヒーそのものの性質と、栄養学的な見方では、ちょっと違う顔を持っているんです。
この記事を読めば、そんなコーヒーのpH(ペーハー)の秘密がスッキリわかるはず。コーヒーの酸味や苦味がどう決まるのか、アルカリ性の水で淹れると味がどう変わるのか、そしてそれが私たちの健康にどんな影響があるのかまで、わかりやすく解説していきます。
自分に合ったコーヒー選びや、新しい淹れ方のヒントも見つかるかもしれません。
コーヒーは酸性?アルカリ性?pHとの関係
コーヒーが酸性かアルカリ性か、これはよくあるギモンですね。
実は、液体の性質を示す「pH」と、食品を分類するときの考え方の違いがポイントになります。
飲むときのコーヒーと、栄養学で見るコーヒーは、ちょっと評価の仕方が違うんです。
pHは液体の性質を0から14の数値で示すもの
まず、「pH」って何でしょう?これは、液体が酸っぱい(酸性)のか、苦い(アルカリ性)のか、それともどっちでもない(中性)のかを示すモノサシみたいなものです。
0から14までの数字で表されて、真ん中の7が中性。7より小さいと酸性、大きいとアルカリ性になります。
pHは、液体の中にどれだけ水素イオン(H+)があるかで決まります。
酸性だと水素イオンが多くて、アルカリ性だと少ないんですね。このpHを測るのには、pHメーターという機械がよく使われます。食品の品質管理なんかにも、このpHはとっても大事な役割を果たしているんですよ。
コーヒーのpHは5.0から6.0の弱酸性
じゃあ、私たちが飲むコーヒーのpHはどれくらいなのでしょうか。
だいたい、ブラックコーヒーでpH5.0~6.0くらい。「弱酸性」というグループに入ります。中煎りだとpH5.0くらい、深煎りになるとpH5.6くらいになることもあるようです。
コーヒーが酸っぱい感じがするのは、豆に含まれる色々な酸のおかげ。クロロゲン酸とかクエン酸とか、そういったものがコーヒー独特の味を作っています。
焙煎の深さや豆の種類でも、このpHは変わってきます。浅煎りだと酸味が強くてpHが低め、深煎りだとpHが上がって酸味はマイルドになる傾向があるでしょう。
栄養学ではコーヒーを代謝後のミネラルでアルカリ性食品に分類
飲むときは弱酸性のコーヒーですが、栄養学の世界では「アルカリ性食品」と呼ばれることがあります。
これは、飲んだときのpHではなくて、体の中で消化された後に残るミネラルの性質で分けているからなんです。
食品を燃やして灰にして、その灰を水に溶かしたときのpHで、酸性食品かアルカリ性食品かを判断する方法があります。灰の中にカリウムやカルシウムが多いとアルカリ性食品、リンや硫黄が多いと酸性食品というわけです。
コーヒー豆にはカリウムが多いので、この分け方だとアルカリ性食品になるんですね。
この「酸性食品・アルカリ性食品」という分け方は、昔の栄養学で使われていましたが、今は科学的な根拠について色々な意見があって、教科書からは消えたりもしています。
コーヒーが「アルカリ性」と言われる本当の理由
コーヒーは飲むと弱酸性なのに、栄養学では「アルカリ性食品」と言われることがある。なんだか不思議ですよね。
ここでは、なぜそう言われるのか、そしてそれが私たちの体にどう影響するのかを、もう少し詳しく見ていきましょう。
食品の酸性やアルカリ性は燃焼後の灰に含まれるミネラルで決定
食品を栄養学的に酸性かアルカリ性かで分けるのは、その食べ物自体の味やpHとはちょっと違います。
これは、食べ物を燃やした後に残る「灰」の性質で決まるんです。灰を水に溶かして、その水のpHを測って判断するんですね。
灰にカルシウムやカリウムみたいなミネラルが多いと、水に溶かすとアルカリ性になるので「アルカリ性食品」。
逆に、リンや硫黄が多いと酸性になるので「酸性食品」というわけです。
だから、梅干しみたいに酸っぱいものでも、灰にアルカリ性のミネラルが多ければアルカリ性食品になるんです。
コーヒーのカリウムがアルカリ性食品と言われる主な根拠
コーヒーがアルカリ性食品と言われるのは、主にこの灰に含まれるカリウムのおかげなんです。コーヒー豆には、アルカリ性を示すミネラルであるカリウムがたくさん含まれています。
コーヒー1杯(約150ml)にも、結構な量のカリウムが入っているんですよ。
食べ物が体の中で使われた後、ミネラルは体の中に残ります。コーヒーの場合はカリウムが多いので、「アルカリ性を示す灰」ができると考えられて、アルカリ性食品に分類されるというわけです。
コーヒー摂取による体全体のpHへの直接的影響はなし
コーヒーが栄養学的に「アルカリ性食品」だからといって、コーヒーを飲んだら体全体がアルカリ性になるわけではありません。
私たちの体には、血液などのpHをすごく狭い範囲(血液ならだいたいpH7.35~7.45)に保つための、強力な仕組みが備わっています。
このpHを保つ仕組みは、血液の中の成分だったり、肺での呼吸だったり、腎臓での調整だったり、色々なものが協力して働いています。
なので、健康な人なら、食べたものや飲んだもので体全体のpHが大きく変わることはないんです。コーヒーを飲んで胃酸が出やすくなることはありますが、それは胃の中だけの話で、体全体のpHとは別問題と考えられます。
淹れる水によるコーヒーの味の変化とアルカリ性の水の影響
コーヒーの味を決めるものは多くありますが、「水」もすごく大事。
コーヒー1杯の98%以上は水ですから、使う水のpHやミネラルの量が、味に大きく影響するんです。
ここでは、水のpHがコーヒーの味にどう関わるか、特にアルカリ性の水だとどうなるかを見ていきましょう。
水のpHがコーヒーの酸味・苦味・コク・香りを左右する
水はただコーヒーを溶かすだけじゃなくて、味を作る「材料」の一つ。水のpHやミネラルのバランスが、コーヒー豆の成分と反応して、味や香りを変えるんですよ。
ざっくり言うと、こんな感じです。
- 酸性の水(pHが低い):コーヒーの酸味が際立ちます。酸っぱい豆だと、ちょっと刺激的すぎるかもしれません。
- アルカリ性の水(pHが高い):コーヒーの酸味を和らげて、まろやかにしてくれます。でも、アルカリ性が強すぎると、味がぼやけたり、粉っぽく感じたりすることも。香りも少し弱くなるかも、という話もあります。
- 中性の水(pH7くらい):バランスよく、豆の個性を引き出しやすいと言われています。
pHだけじゃなく、水に含まれるミネラルの量(硬度)も大事。
マグネシウムは甘みを、カルシウムはコクを引き出します。硬水すぎると雑味が出たり、逆に軟水すぎると味が薄くなったりすることもあるでしょう。
アルカリ性の水はコーヒーの酸味を和らげまろやかにするが注意点もある
アルカリ性の水でコーヒーを淹れると、一番わかりやすいのは酸味が和らいで、口当たりがまろやかになること。
アルカリ性の水が、コーヒーの酸っぱい成分を中和してくれるからですね。酸味が苦手な人には良いかもしれません。
ある実験では、pH8.8~9.4の弱アルカリ性の水で淹れたコーヒーは、「より丸みがあり、酸味が控えめで甘さを強く感じる結果」になったそうです。
でも、注意点も。アルカリ性が強すぎると、酸味が消えすぎて味がぼんやりしたり、コーヒーらしさがなくなったりすることも。香りも少し弱くなるかもしれません。
アルカリイオン水の中には、独特の風味があるものもあって、それがコーヒーの味を変えてしまうこともあるでしょう。
どんな豆に使うかでも結果は変わります。元々酸味が少ない豆だと味がぼやけるかもしれないし、すごく酸っぱい豆ならちょうどよくなるかもしれません。
美味しいコーヒーには中性から弱アルカリ性の軟水・中硬水が基本
じゃあ、どんな水がいいの?という話ですが、多くのプロは中性から弱アルカリ性(pH7.0~8.0くらい)で、軟水から中硬水をすすめています。
ただ、pH6.0~7.0の少し酸性寄りがいいという意見もあり、目指す味で変わるみたいですね。極端なのは避けた方がよさそうです。
水の硬度も大事。
- 軟水(ミネラル少なめ):豆の繊細な酸味や香りが出やすいです。フルーティーな豆に合うでしょう。
- 中硬水(ミネラルほどほど):バランスが良く、色々な豆に合います。
- 硬水(ミネラル多め):コクや苦味が出やすいです。深煎りに合うことも。でも、硬すぎると雑味が出たりします。
日本の水道水は、だいたい軟水~中硬水でpHも中性くらいなので、コーヒーには割と向いていると言われます。
ただ、塩素(カルキ)は味を邪魔するので、浄水器を使ったり沸騰させたりするといいですね。
【体験談】アルカリ性の水でのコーヒー抽出
理論も大事だけど、やっぱり実際に飲んでみないとね!ということで、アルカリ性の水でコーヒーを淹れたらどうなるか、簡単な飲み比べをしてみました。
いつもと同じ豆・水・抽出条件での飲み比べ結果
比べるものが違うと意味がないので、条件はできるだけ揃えました。
- コーヒー豆:いつも飲んでる中煎りのスペシャルティコーヒー。
- いつもの水:浄水器を通した水道水(ほぼ中性、軟水)。
- 試す水:市販のアルカリイオン水(pH8.8~9.0程度)。
- 淹れ方:ハンドドリップで、豆の量、お湯の温度、淹れる時間は全部同じにしました。
これで、いつもの水とアルカリイオン水、それぞれでコーヒーを淹れて、飲み比べてみました。
アルカリ水で淹れたコーヒーは香りが穏やかで酸味もまろやかに変化
まず香り。アルカリイオン水で淹れた方は、いつものコーヒーより香りが少しおとなしい感じ。いつもの方が、華やかな香りがしました。これは、「香りがやや弱い」という報告と似ていますね。
次に味。一番違ったのは、やっぱり酸味。いつものコーヒーは、豆らしいスッキリした酸味があるんですが、アルカリイオン水の方は、その酸味のカドが取れて、すごくまろやか。刺激が少なくて、飲みやすい感じでした。
酸味が抑えられた分、甘みを感じやすくなったのも面白かったです。
酸味が苦手な人や味の変化を楽しみたい人にアルカリ水コーヒーは一つの方法
普段からコーヒーの酸味を楽しんでいる私には、アルカリイオン水の方が「美味しい!」とは正直思えませんでした。豆の個性が少し隠れちゃったかな、と。
しかし、これは好みの問題。コーヒーの酸味が強すぎるのが苦手な人や、胃の調子で酸味が気になる人(これは味の感じ方の話で、体全体のpHが変わるわけじゃないですよ)には、アルカリ性の水はコーヒーを飲みやすくしてくれる良い方法かもしれません。
コーヒーとアルカリ性に関するよくある質問
コーヒーの酸性・アルカリ性って、なんだかややこしいですよね。よくある質問をまとめてみました。
【まとめ】コーヒーとアルカリ性の知識で毎日のコーヒーをより豊かに
コーヒーの酸性・アルカリ性について、pHのこと、栄養学的な話、水の影響など、色々な角度から見てきました。
最後に大事なポイントをまとめましょう。
まず、コーヒーは飲むときは弱酸性(pH5.0~6.0くらい)だけど、栄養学的には「アルカリ性食品」ということ。
これは、体の中でアルカリ性を示すミネラル(カリウムとか)が多いから。しかし、これを飲んだからって体全体がアルカリ性になるわけじゃなくて、私たちの体はちゃんとpHバランスを保つ仕組みがあります。
次に、コーヒーの味は、淹れる水のpHやミネラルの量(硬度)で大きく変わということ。
アルカリ性の水は酸味を和らげてまろやかにしますが、それがベストとは限りません。一般的には、中性~弱アルカリ性の軟水~中硬水が、豆の個性を引き出しやすいと言われています。
こういう知識があると、ただコーヒーを飲むだけじゃなくて、もっと意識的に選んだり、淹れ方を変えてみたりできますよね。酸味が苦手なら、水を変えたり、深煎りの豆にしたり、低酸性コーヒーを試したり。
この記事で知ったことを参考に、自分の好みや体調に合わせて、色々なコーヒーを楽しんでみてください。